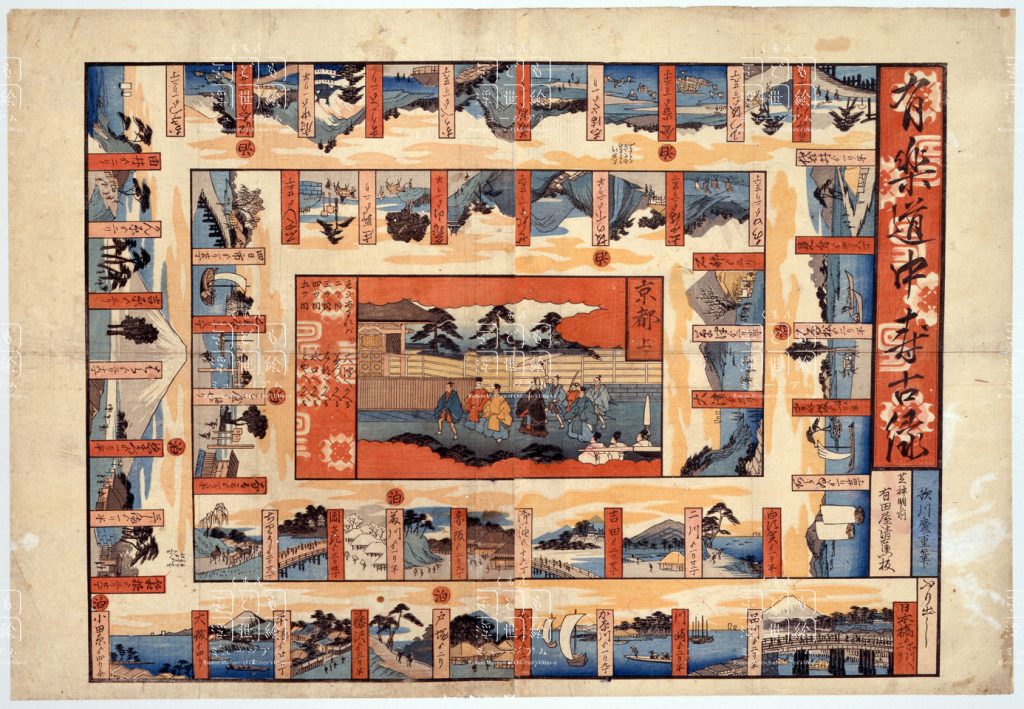
有楽道中寿古録
天保頃 (1830-1844)
- 資料名1
- 有楽道中寿古録
- 史料名1よみ
- ゆうらくどうちゅうすごろく
- 史料名Roma1
- yuurakudouchuusugoroku
- 絵師・著者名
- 歌川 廣重(歌川 広重*)
- Creator
- 落款等備考
- 歌川 廣重筆
- 板元・製作者
- 有田屋清兵衛
- 制作年和暦
- 天保頃
- 制作年西暦
- 1830-1844
- 書誌解題
- 資料名1
- 有楽道中寿古録
- 資料名2
- 史料名1よみ
- ゆうらくどうちゅうすごろく
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- yuurakudouchuusugoroku
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 有楽道中寿古録
- 絵師・著者名
- 歌川 廣重(歌川 広重*)
- 絵師・著作者名よみ
- ひろしげ (うたがわ ひろしけ)゛
- Creator
- 管理No.
- 00000092
- 管理No.枝番号
- 落款等備考
- 歌川 廣重筆
- 板元・製作者
- 有田屋清兵衛
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 天保頃
- 制作年西暦
- 1830-1844
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大大判 大倍判
- 印章の有無
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- おもちゃ絵 風景画
- 内容2
- ゲーム 道中
- 内容3
- 双六 道中 東海道
- テーマ
- 江戸後期になると旅の規制が弱まり、伊勢参りなど旅が庶民の娯楽となった。特に十返舎一九の『東海道中膝栗毛』(文化6年完結)や広重の浮世絵「東海道五拾三次」の人気によって絵双六でも数多くの「東海道中」が作られたが、その代表作である。題の有楽は遊楽や行楽と同じで、遊び楽しむことである。
- 具体物
- 「ふり出し」はお江戸「日本橋」を旅立つ人々で、背後には松林に囲まれ江戸城が見え、富士がそびえている。日本橋の文字の下には「より品川二り」とあり、各枡目ごとに次の宿までの距離を示してある。風景画、特に東海道で知られる広重の作品だけに、各宿場の特色ある風物をたくみに表現している。枡目にとらわれずに、相模湾や駿河湾、富士山などはワイドな画面構成で雄大な風景を楽しませてくれる。上りは「京都」で、御所に参内する大名、従者が長柄の傘をさしかけている。
- Comments
- 位置づけ
- 五街道で最も重要な東海道中五十三次を、人気絵師広重が描いたもので、道中双六の代表作である。子どもたちは、京への旅を双六で楽しみながら地理を学んだ。
- 讃・画中文字
- ふり出し→日本橋→品川→川崎→かな川→ほどがや→泊 戸塚→藤沢→平塚→大磯→泊 小田原→箱根→三しま→泊 ぬまづ →はら→吉原→かん原→由井→おきつ→泊 えじり→府中→まりこ→おかべ→藤枝→しまだ→泊 金谷→ひ坂→かけ川→袋井→見付→泊 はま松→まい坂→あらい→白須賀→二川→吉田→御油→赤坂→泊 藤川→岡さき→ちりゅう→なるみ→泊
三屋→くわな→四日市→石やくし→庄野→亀山→せき→泊 坂の下→土やま→水口→石部→草津→大津→京都上「一つあまれば大津へかへる 二つ同草津 三つ同石部 四つ同水口 五つ同みやへかえる
- 自由記入欄
- 遊び方「回り双六」だだ上りを行きすぎた場合は、それぞれ行きすぎた数によって、もどる場所が指定されている。
・改印がなく、時代は確定できないが、広重の「東海道五拾三次」が人気を得た天保から、弘化頃と思われる。
・広重は数多くの東海道双六を手がけているが、本品はどの絵双六本にも紹介されておらず、貴重である。
・絵師名が斎号と雅号でなく、歌川広重と画姓・雅号で記されているのも珍しい。
- 史料分類
- 絵画
