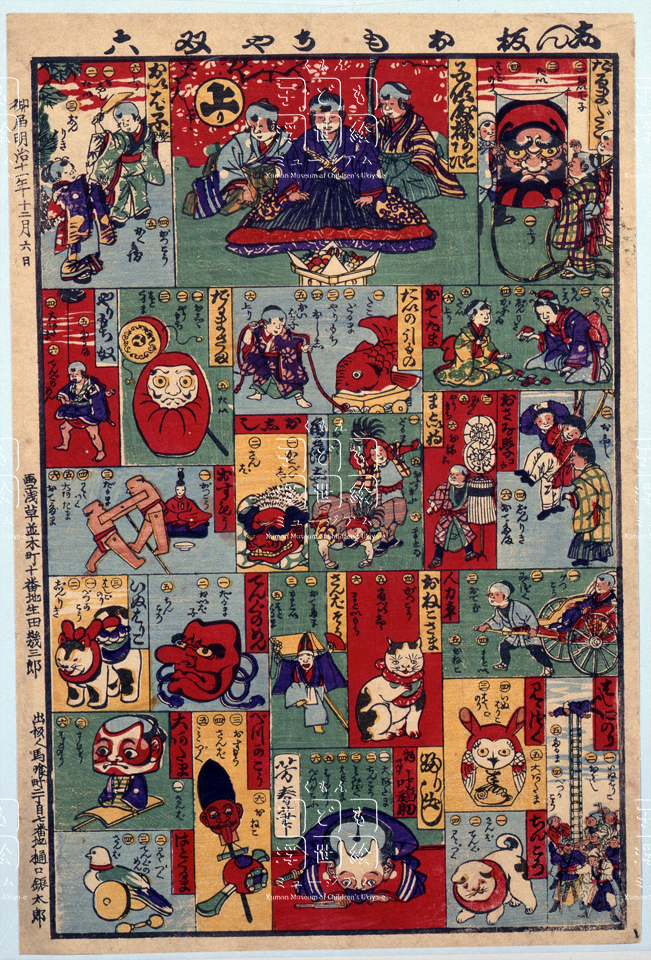
志ん板おもちゃ双六
明治11年 (1878)
- 資料名1
- 志ん板おもちゃ双六
- 史料名1よみ
- しんぱんおもちゃすごろく
- 史料名Roma1
- shinpanomochasugoroku
- 絵師・著者名
- 芳春
- Creator
- 落款等備考
- 板元・製作者
- *
- 制作年和暦
- 明治11年
- 制作年西暦
- 1878
- 書誌解題
- 資料名1
- 志ん板おもちゃ双六
- 資料名2
- 史料名1よみ
- しんぱんおもちゃすごろく
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- shinpanomochasugoroku
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 志ん板おもちゃ双六
- 絵師・著者名
- 芳春
- 絵師・著作者名よみ
- よしはる (うたがわよしはる)
- Creator
- 管理No.
- 00000133
- 管理No.枝番号
- 落款等備考
- 板元・製作者
- *
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 明治11年
- 制作年西暦
- 1878
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大判
- 印章の有無
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- おもちゃ絵
- 内容2
- ゲーム
- 内容3
- 双六 おもちゃ 玩具
- テーマ
- よし藤「新政おもちゃ双六」(1002)を明治になって改訂したもので
新しいものが8点登場している。人気玩具を扱った双六であることは
同じで、画面の構成も同一だが、明治になって新しく何かが加わり
何が消えたかが、注目される。
- 具体物
- 「ふり出し」は叶福助で、この縁起人形が明治になっても益々人気のあったことが
うかがえる。「上り」は菓子を前にした子供の殿様で、江戸時代への郷愁か
背景は前回と同じ桜だ。新しく登場したもので注目されるのは「おさな学コウ」で
幼稚園を示し、女先生とブランコを楽しむ洋服姿の幼児だ。平安時代に大陸伝来の
ブランコ「鞦韆」はあったが次第にすたれ、明治になって西洋から伝わり幼稚園で
盛んになる。「人力車」は、明治2年に日本で考案された乗物だ。
「大あたま」は、題は同一だが、お面から飛び人形へと変わっている。
- Comments
- 位置づけ
- 今でいえば著作権侵害の盗作だが、当時はよう行われた。文久1年から明治維新を経て
17年後(明治11年)の玩具・遊びの変遷を示す貴重な資料ともいえる。
- 讃・画中文字
- おいばね(子供殿様あそび)上り、だるまだこ
やりもち奴、だるまさま、たいの引もの、(おてだま)
おすもう、<おしし>、(角兵衛じし)、(まとい持)、(おさな学コウ)
<いぬはりこ>、<てんぐのめん>、<さんばそう>、(おねこさま)、(人力車)
大あたま、べっかこう、みつづく、はしごのり
はとぐるま、ふり出し(叶福助)、ちんころ
( )は新しく登場したもの、< >は画面での位置が移動したもの。
(中城正堯氏翻刻)
- 自由記入欄
- 遊び方=飛び双六
- 史料分類
- 絵画
