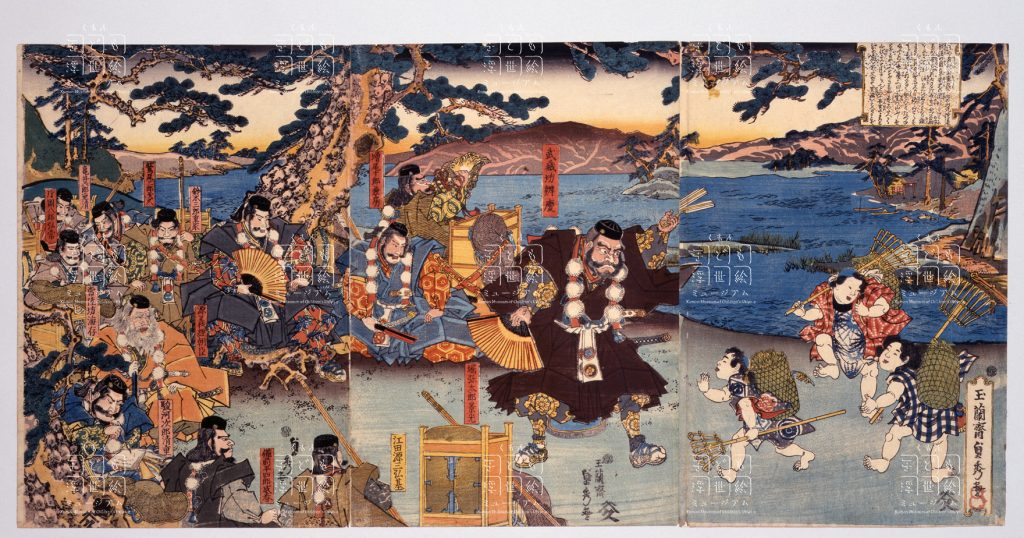
武蔵坊弁慶・源義経
天保弘化頃 (1830-1848)
- 資料名1
- 武蔵坊弁慶・源義経
- 史料名1よみ
- むさしぼうべんけい・みなもとのよしつね
- 史料名Roma1
- musashiboubenkeiminamotonoyoshitsune
- 絵師・著者名
- 玉蘭斎 貞秀(歌川 貞秀)
- Creator
- 落款等備考
- 玉蘭斎 貞秀画
- 板元・製作者
- 山本屋 平吉(山久)
- 制作年和暦
- 天保弘化頃
- 制作年西暦
- 1830-1848
- 書誌解題
- 資料名1
- 武蔵坊弁慶・源義経
- 資料名2
- 史料名1よみ
- むさしぼうべんけい・みなもとのよしつね
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- musashiboubenkeiminamotonoyoshitsune
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 武蔵坊弁慶・源義経 <安宅関>
- 絵師・著者名
- 玉蘭斎 貞秀(歌川 貞秀)
- 絵師・著作者名よみ
- さだひで (ぎょくらんさい さだひで/うたがわ さだひで)
- Creator
- 管理No.
- 00000273
- 管理No.枝番号
- 000
- 落款等備考
- 玉蘭斎 貞秀画
- 板元・製作者
- 山本屋 平吉(山久)
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 天保弘化頃
- 制作年西暦
- 1830-1848
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大判3枚続
- 印章の有無
- 名主 版元
- 印章内容
- 名主:村松
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- 子ども物語絵
- 内容2
- 武者絵
- 内容3
- 安宅関 英雄豪傑 武蔵坊弁慶 源義経 子ども 童
- テーマ
- 義経の北国落ちで、安宅の関にかかる前段の場面である。奥州に脱出するため北陸路をたどり、加賀の国・安宅の関に近づいた山伏姿の義経一行から、弁慶が出て、松葉かきの子どもたちに「この関は山伏を通すか?」たずねている。「通し申す」との答えを得て、ほうびに扇を与え、関所へと向かう。
- 具体物
- 右3人が松葉かきの子どもで、松葉をかく熊手を持ち、かごを背負っている。中央に立っているのが弁慶で、左手の扇を子どもたちに与えようとしている。左手の松の根元に扇を手に座る人物が義経。その右に義房、左に海存(尊)がいる。義経一行は全員山伏姿で、頭巾(ときん)をかぶり、胸に結袈裟(ゆいげさ)をかけ、笈(おい)を背負い金剛杖を持っている。ほら貝を吹く者や、筆を走らせる者もいる。舞台は砂浜に松林が続く、美しい加賀の海辺である。
- Comments
- 位置づけ
- 義経一代記でも子どものからむ場面は珍しく、また子どもによる松葉かきの風俗もよく描かれている。幕末の人気絵師貞秀だけに、厳めしい山伏姿の一行と無邪気な子どもがよく対比され、背景の松と海浜の描写も見事である。
- 讃・画中文字
- 武蔵坊弁慶・源義経
源の義経公、奥州下向の時、北陸道・越後の国なる安宅の関にかゝりけるに、草かる童のむれゐけるに弁慶心づき、扇を三本とり出し、「汝らにたづぬることあり。誠をいはゞ、これを得させん。もし偽らば、とらすまじ」。童は、只よねんなく「何ごとをたづね給ふ」といふ。弁慶、又曰。「此関は山ぶしをとほすや、又とほさすや」。童こたへて「山伏をばとほし申す也」といふ。弁慶よろこび、かの扇をあたへ、やがて関路をこへけるとぞ。
(小泉吉永氏翻刻)
- 自由記入欄
- 公文教育研究会は右面の版下も所蔵しており、貴重。
- 史料分類
- 絵画
