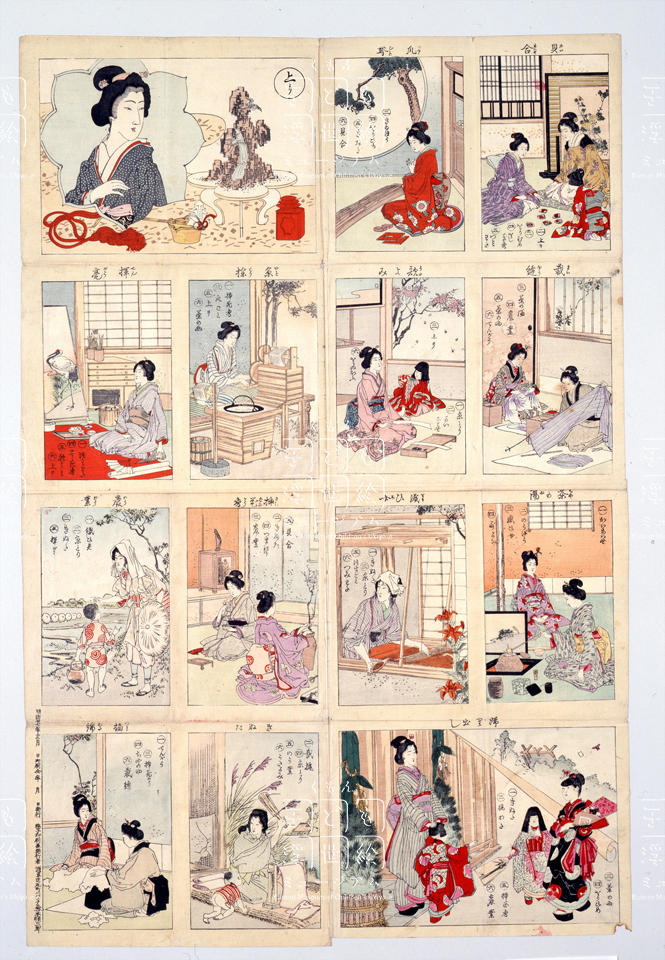
女礼式双六
明治27年 (1894)
- 資料名1
- 女礼式双六
- 史料名1よみ
- おんなれいしき すごろく
- 史料名Roma1
- onnareishikisugoroku
- 絵師・著者名
- 未詳
- Creator
- 落款等備考
- 板元・製作者
- *
- 制作年和暦
- 明治27年
- 制作年西暦
- 1894
- 書誌解題
- 資料名1
- 女礼式双六
- 資料名2
- 史料名1よみ
- おんなれいしき すごろく
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- onnareishikisugoroku
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 女礼式双六
- 絵師・著者名
- 未詳
- 絵師・著作者名よみ
- Creator
- 管理No.
- 00000424
- 管理No.枝番号
- 落款等備考
- 板元・製作者
- *
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 明治27年
- 制作年西暦
- 1894
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- *
- 印章の有無
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵 近代版画
- 種別2
- 錦絵 木版画
- 種別3
- ゲーム
- 内容1
- おもちゃ絵
- 内容2
- ゲーム
- 内容3
- 双六 女子 女性 生涯 稽古事
- テーマ
- 上流階級だけでなく、また未婚女性だけでもなく、家庭での女性のあるべき姿をテーマとしている。江戸時代の「教訓いろは歌絵抄」(345)に「月も花もめでて家をもおさめつつ雪や蛍の学びをもせよ」を受け継いだ内容で、さまざまな家事、家業をしっかりこなしながら、風流も楽しむことを教えている。
- 具体物
- 「ふり出し」は、正月の女子の楽しみの羽根つきだが、門松とともに遠景には神社が描かれているところが明治らしい。「上り」は婚礼を象徴する三三九度の柄杓と杯、長寿の象徴、寿山石が美人に添えてある。枡目の題材は家事、家業がきぬた打ち、摘綿(真綿のばし)、機織、農業、裁縫、糸とり(糸くり)であり、教養、けいこ事が茶の湯、和歌、書画、見合せ、琴である。身分制度がなくなり、没落士族の子女が芸事で身を立てるなどの世相もうかがえる。
- Comments
- 位置づけ
- 明治らしい女性像を反映している。
- 讃・画中文字
- 上り 爪琴 見合
揮毫 糸操 歌よみ 裁縫
農業 挿花 織ひ女 茶の湯
摘綿 きぬた ふり出し
- 自由記入欄
- 遊び方「飛び双六」
- 史料分類
- 絵画
