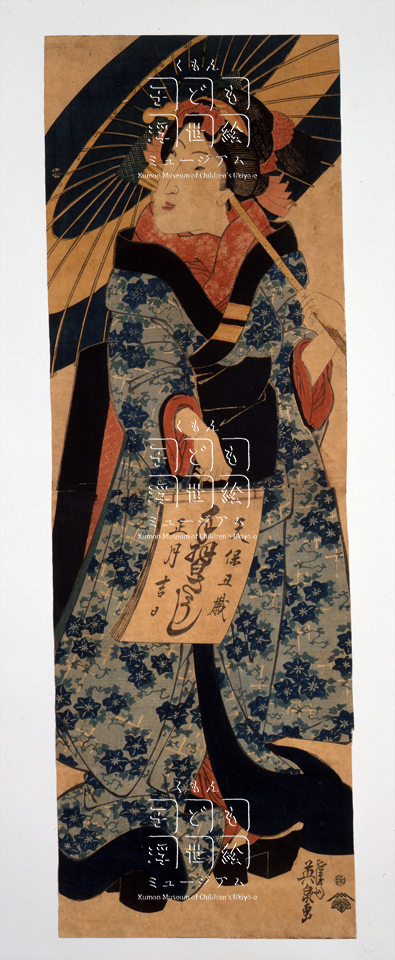
〈手習い草紙を持つ娘〉
天保12年 (1841)
- 資料名1
- 〈手習い草紙を持つ娘〉
- 史料名1よみ
- てならいそうしをもつむすめ
- 史料名Roma1
- 絵師・著者名
- 渓斎 英泉
- Creator
- 落款等備考
- 渓斎英泉画
- 板元・製作者
- 蔦屋重蔵
- 制作年和暦
- 天保12年
- 制作年西暦
- 1841
- 書誌解題
- 資料名1
- 〈手習い草紙を持つ娘〉
- 資料名2
- 史料名1よみ
- てならいそうしをもつむすめ
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 〈手習い草紙を持つ娘〉
- 絵師・著者名
- 渓斎 英泉
- 絵師・著作者名よみ
- えいせん (けいさい えいせん)
- Creator
- 管理No.
- 00000633
- 管理No.枝番号
- 000
- 落款等備考
- 渓斎英泉画
- 板元・製作者
- 蔦屋重蔵
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 天保12年
- 制作年西暦
- 1841
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大判竪2枚続
- 印章の有無
- 極 版元
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- 人物画
- 内容2
- 美人
- 内容3
- 学ぶ 手習い 傘 舞踊「手習子」
- テーマ
- 歌舞伎所作事(舞踊)の「手習子」を描いている。踊りは、寺子屋帰りのおませな町娘が、春の野原で道草をくって、傘や手習双紙を手に、蝶と戯れる場面だ。
- 具体物
- 竪二枚の画面いっぱいに踊り子が描かれている。右手の手習い帳には「天保丑歳 手習さうし 正月吉日」とあり、天保12年の正月から使い始めた帳面であることと、画の作成年代が読み取れる。左手では、蛇の目の傘を持っている。花柄の衣装の裾は長くて足下を隠しており、舞踊ならではだ。寺子屋通いの娘とはいえ、もう年頃で色気を感じさせる。
- Comments
- 位置づけ
- 江戸後期には、江戸では娘の寺子屋通いも、おけいこ通いも一般化していた。それを反映した踊であり、浮世絵である。この踊りの人気のあったことがうかがえる。舞台での本格的な踊り場面だ。
- 讃・画中文字
- 自由記入欄
- 題:画中に「手習さうし」とあり、漢字では「手習双紙」ないし「手習草子」で、手習の練習帳だ。しかし、この作品は舞踊の描写であり、舞踊の題名「手習子(てならいこ)」を画の題名にしたい。
同じテーマの作品に、貞房「子供 手ならい双紙」がある。
- 史料分類
- 絵画
