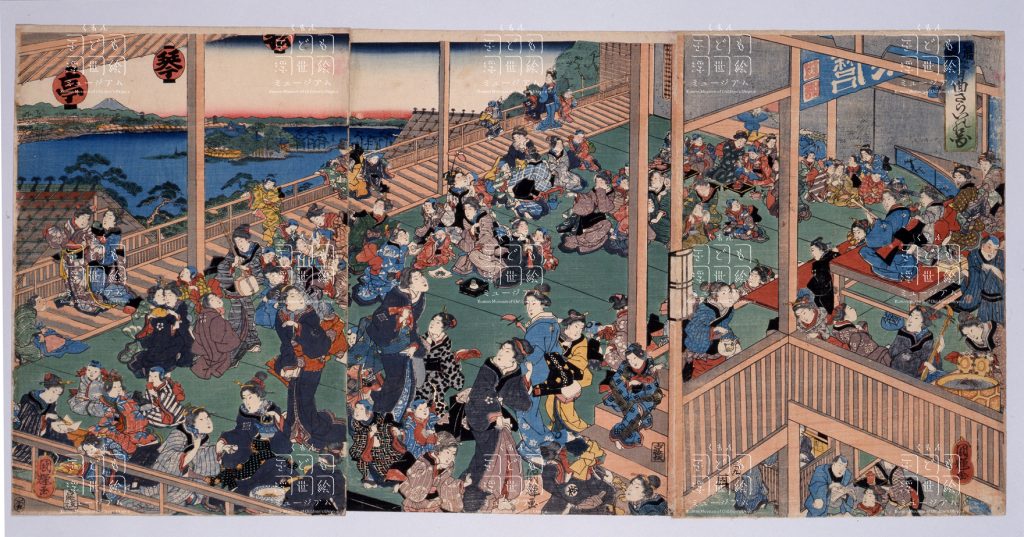
湯島 音曲さらいの図
安政5年 (1858)
- 資料名1
- 湯島 音曲さらいの図
- 史料名1よみ
- ゆしまおんぎょくさらいのず
- 史料名Roma1
- yushima ongyokusarainozu
- 絵師・著者名
- 國輝(歌川 国輝)
- Creator
- 落款等備考
- 國輝画
- 板元・製作者
- *
- 制作年和暦
- 安政5年
- 制作年西暦
- 1858
- 書誌解題
- 資料名1
- 湯島 音曲さらいの図
- 資料名2
- 史料名1よみ
- ゆしまおんぎょくさらいのず
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- yushima ongyokusarainozu
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 湯島 音曲さらいの図
- 絵師・著者名
- 國輝(歌川 国輝)
- 絵師・著作者名よみ
- くにてる (うたがわ くにてる)
- Creator
- 管理No.
- 00000693
- 管理No.枝番号
- 000
- 落款等備考
- 國輝画
- 板元・製作者
- *
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 安政5年
- 制作年西暦
- 1858
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大判3枚続
- 印章の有無
- 年月 板元
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- 子ども絵
- 内容2
- 手習い
- 内容3
- 音曲
- テーマ
- 音曲さらいとは、三味線や琴など邦楽の師匠が、日常教えた芸を、日を定めて演じさせる会で「さらえ」とか「おさらい」ともいう。なぜ音曲稽古が盛んだったか、江戸後期の風俗百科『守貞漫稿』には、「江戸の子は一芸に習熟し、それをもって武家に仕えないと良縁に恵まれない」と述べてある。これは音曲師匠の弟子達による、いわば成果発表会でり、その賑わいぶりがよく表現されている。
- 具体物
- ここは、上野不忍池を見下ろす湯島の料亭「松琴亭」の大広間である。右手に緋毛氈(ヒモウセン=フェルト)を敷いた演台があり、4人が浄瑠璃なのか演じており、手前の一人は三味線を手にしている。そばには、ご祝儀(しゅうぎ)の菓子折を持つ男がいる。演台の前方では、家族連れが膳を囲んでお茶菓子を食べながら、見物している。左手では、ちょうちょの玩具で遊んだり、浮世絵を眺めたりする親子もいる。手前では、次の出番の子どもたちの面倒を師匠が見ているようだ。左の縁側では、娘の髪を整える母がいる。上部には「松琴亭」の軒提灯が下がっている。右下には階下が見えており、ここは二階だ。また演台を置いた上段に上る階段も見えている。この松琴亭は、斎藤月岑(さいとうげっしん)著『東都歳事記』にも挿絵入りで紹介されている。
- Comments
- 位置づけ
- 江戸後期に音曲けいこ、およびその「さらい」がいかに盛んであったかを、具体的に示す貴重な作品である。会場が実在した湯島の松琴亭であることも分かり、資料性が高い。母のわが子への注力ぶりも、よくうかがえる。
- 讃・画中文字
- 自由記入欄
- 史料分類
- 絵画
