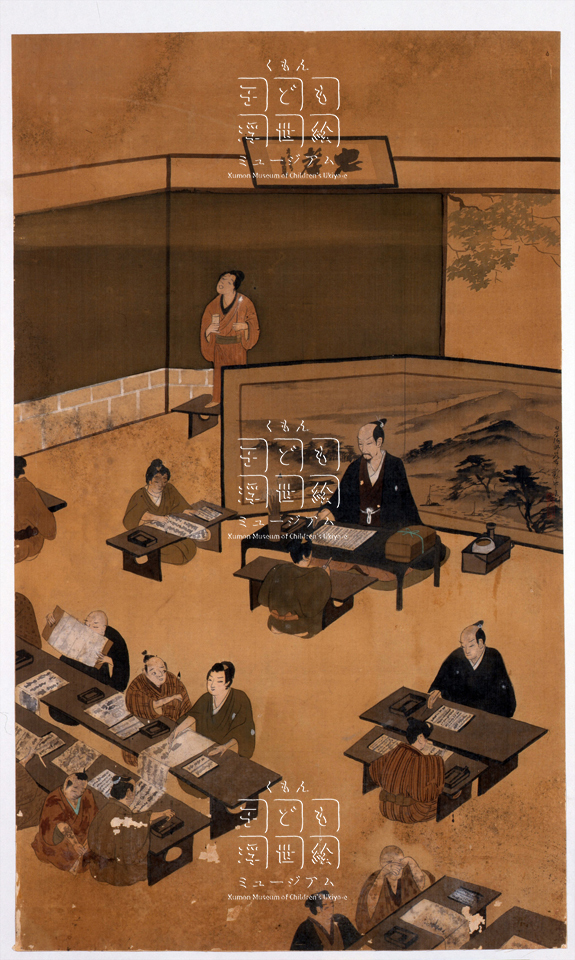
寺子屋の図
- 資料名1
- 寺子屋の図
- 史料名1よみ
- てらこやのず
- 史料名Roma1
- terakoyanozu
- 絵師・著者名
- 未詳
- Creator
- 落款等備考
- 板元・製作者
- 未詳
- 制作年和暦
- 制作年西暦
- 書誌解題
- 資料名1
- 寺子屋の図
- 資料名2
- 史料名1よみ
- てらこやのず
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- terakoyanozu
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 寺子屋の図
- 絵師・著者名
- 未詳
- 絵師・著作者名よみ
- Creator
- 管理No.
- 00001023
- 管理No.枝番号
- 落款等備考
- 板元・製作者
- 未詳
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 制作年西暦
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- その他
- 印章の有無
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 肉筆浮世絵
- 種別2
- 種別3
- 内容1
- 風俗画
- 内容2
- 手習い絵
- 内容3
- 寺子屋 学習
- テーマ
- 寺子屋を描いた彩色肉筆画であるが、武士ないしは浪人が師匠の厳しい学習風景を描いてある。いわゆる「雷師匠」が教える寺子屋で、その教室風景をよくとらえてある。特に寺子屋では基本的には生徒の進度ごとに、往来物(教科書)が与えられ、個別に指導を受けると、あとは手習いを中心に自学自習をおこない、適宜師匠のチェック・指導をうけ、与えられた課題を習得していると、新しい課題に進んだ。怠けたりいたずらをすると、罰があった。それらがよく表現されている。
- 具体物
- 風の前に座った厳めしい師匠がおり、一人の寺子(生徒)を呼んで読み書きの成果を確認し、指導している。生徒は、自分の天神机を運んで、個人指導を受けている。その右手(画面左)には、次に指導を受けると思われる生徒が、控えている。画面右手前には助手の指導者がおり、やはり一人を指導している。左手前では、寺子達がたがいに向き合う形で机を並べ、各自お手本を自学自習で書写しているが、隣同士で話す子もいる。画面下端の子はどうやら泣いているようだ。部屋の後部には「忠孝」の額が掛けてあり、その下には罰をうけ、線香と茶碗を手に机に立たされた子がいる。
- Comments
- 位置づけ
- 寺子屋の肉筆図は大変少ないが、この作品は寺子屋の机の配置から、一人ずつ呼んでの指導ぶり、さらには罰で立たされた子まで、リアルに描いてあり、教育史料として大変貴重である。日本教育史の専門家からの評価も高い。落款がなく、絵師・作画期は未詳であるが、江戸後期の作と思われる。
- 讃・画中文字
- 自由記入欄
- 史料分類
- 絵画
