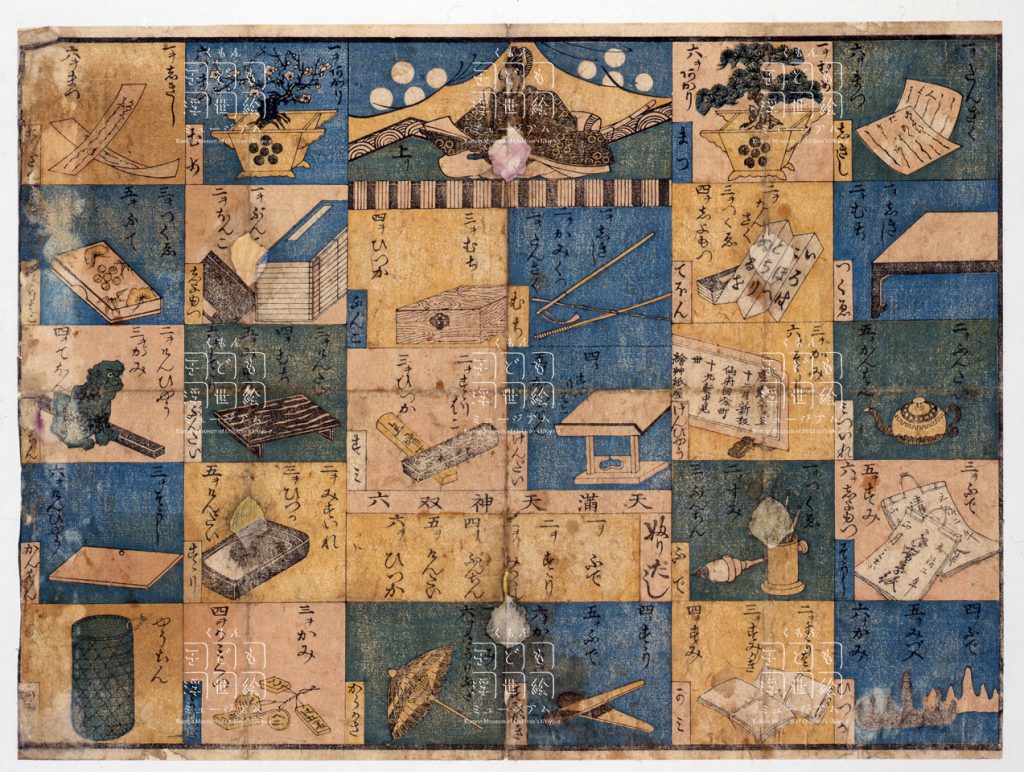
天満天神双六
慶応元年 (1865)
- 資料名1
- 天満天神双六
- 史料名1よみ
- てんまんてんじんすごろく
- 史料名Roma1
- tenmantenjinsugoroku
- 絵師・著者名
- 作者未詳
- Creator
- 落款等備考
- 板元・製作者
- 制作年和暦
- 慶応元年
- 制作年西暦
- 1865
- 書誌解題
- 資料名1
- 天満天神双六
- 資料名2
- 史料名1よみ
- てんまんてんじんすごろく
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- tenmantenjinsugoroku
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 天満天神双六
- 絵師・著者名
- 作者未詳
- 絵師・著作者名よみ
- Creator
- 管理No.
- 00001034
- 管理No.枝番号
- 落款等備考
- 板元・製作者
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 慶応元年
- 制作年西暦
- 1865
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- その他
- 印章の有無
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- おもちゃ絵
- 内容2
- ゲーム
- 内容3
- 双六 天神
- テーマ
- 寺子屋で使う文房具を中心に、寺子屋生活に必要な道具類も含めて双六にしてある。通常の文具以外に、体罰に使うむちや永沈が見られること、仙台の地方版であることが注目される。
- 具体物
- 「ふりだし」は「天満天神双六」という題名と飛び先のみで絵はなく、「上り」は菅原道真像であり、左右の枡目に松と梅を配してある。各枡目の品では、文房具が右下から筆架、紙、墨掻、草紙、筆、硯、水入れ、硯屏、見台、墨、文台、文鎮、机、文庫、硯箱、色紙、短冊で、これに手本と書物が加わり、次いで生活道具から唐傘、草履札、紙屑かご、さらに商売道具として看板と鞭が入っている。大きな寺子屋では、草履を間違えないように札(下足札)を渡していたようだ。
- Comments
- 位置づけ
- 寺子屋で使う文房具、道具類がよく分かり貴重。現在この1枚しか残っていない。
- 讃・画中文字
- 天満天神双六
*「ふりだし」と「上り」を除き、最下段右下から最上段左上までの順に翻字。
○ふりだし
天満天神双六
一ヲ ふで
二ヲ すゝり(硯)
三ヲ みついれ(水入れ)
四ヲ ぶんちん(文鎮)
五ヲ けんたい(見台)
六ヲ ひつか(筆架)
【一段目】
○ひつか
四ヲ ふで
五ヲ みづ入
六ヲ かみ
○かみ
二ヲ すゝりばこ(硯箱)
三ヲ すみかき(墨掻)
四ヲ すみ
○すみかき
四ヲ すゝり
五ヲ ふで
六ヲ からかさ(唐傘)
○からかさ
一ヲ すみ
六ヲ さうりふだ(草履札)
○さうりふだ
三ヲ かみ
四ヲ かみくつ(紙屑)
○かみくつ
やうちん(永沈)
*浄土双六などで、一度そこに落ちると長く
出ることのできない場所を指す。従って、こ
の「紙屑」に来たらゲーム失格となったので
あろう。
【二段目】
○そうし
三ヲ ふで
五ヲ すみ
六ヲ しよもつ(書物)
元治二年 正月 三さい(歳)
手習草紙
元治二年 正月…
清(書草紙)
○ふで
一ヲ つくゑ(机)
二ヲ すみ
三ヲ ぶんちん
○すゝり
二ヲ みすいれ
三ヲ ひつか
五ヲ けんだい
○かんばん
三ヲ そうし
六ヲ けんびやう
【三段目】
○みついれ
二ヲ ふんたい
五ヲ かんはん
○けんびやう(硯屏)
三ヲ かみ
六ヲ そうし
慶応元乙丑十二月新板
仙台国分町十九軒中見世
絵艸紙屋
○けんだい
四ヲ すゝりばこ
五ヲ かんばん
○すみ
二ヲ すゝりばこ
三ヲ ひつか
○ぶんたい
三ヲ けんたい
四ヲ むち
五ヲ みす入
六ヲ すゝり
○ぶんちん
二ヲ けんひやう
三ヲ かみ
四ヲ てほん
【四段目】
○つくゑ
一ヲ しきし
二ヲ むち
○てほん
二ヲ たんさく
三ヲ つくゑ
四ヲ しよもつ
○むち(鞭)
一ヲ しきし
二ヲ かみくつ
三ヲ たんさく
○ふんこ(文庫)
三ヲ むち
四ヲ ひつか
○しよもつ
一ヲ ぶんこ
二ヲほんこ ( 「ぶんこ」か)
○すゝりばこ
三ヲ つくゑ
五ヲ ふて
【五段目】
○しきし
一ヲ たんざく(短冊)
六ヲ まつ
○まつ
一ヲ むめ(梅)
六ヲ あかり(上り)
○むめ
一ヲ あかり
六ヲ まつ
○たんざく
一ヲ しきし
六ヲ まつ
○上り
*菅原道真(菅公)座像
*
*文房四友(文房四宝)などの学用品をモチーフにした双六。左下隅の「かみくつ(紙屑)」に入るとゲーム失格になるのが面白い。
(小泉吉永氏翻刻)
- 自由記入欄
- 遊び方「飛び双六」
・時代は「そうし」の手習草紙・表紙に「元治二年正月」とあり、また「けんびょう」に「慶応元年十二月新板」とあるが、元治二年は四月に慶応になっており、刊行された十二月は慶応である。
・文房具でなじみの薄い物のみ説明すると、筆架は筆をのせかけておく台、墨掻は墨汁、墨滓を掻き集めるへら、硯屏は硯のそばに立ててほこりを防ぐ小さな衝立、見台は書物をのせて読む台、文台は書物や用紙をのせておく台、草履札は下足札と同じ。
・江戸時代には文房具の中でも、紙・筆・墨・硯を文房四宝といって大切にした。この双六にも当然織り込まれている。
- 史料分類
- 絵画
