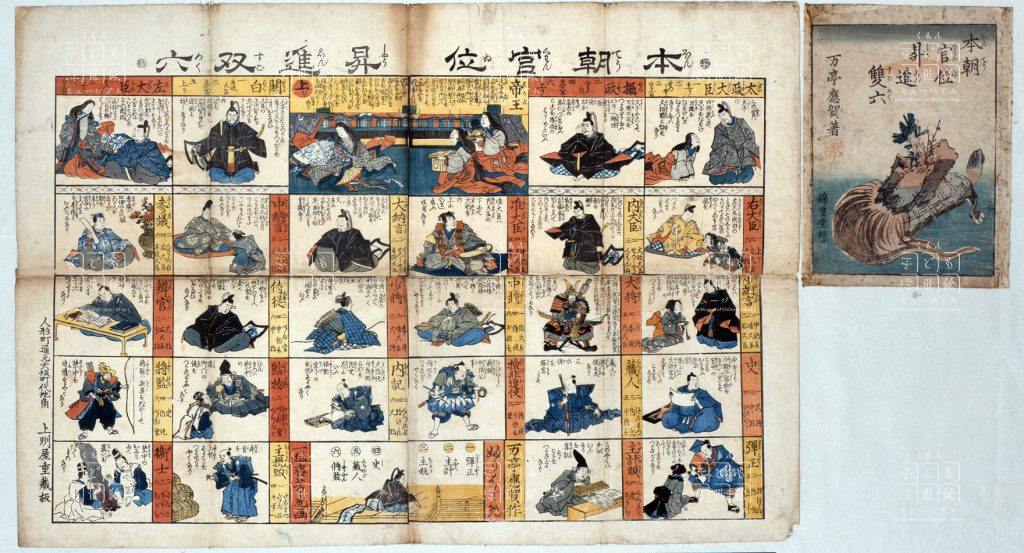
本朝官位昇進双六
弘化4年から嘉永5年 (1847-52)
- 資料名1
- 本朝官位昇進双六
- 史料名1よみ
- ほんちょうかんいしょうしんすごろく
- 史料名Roma1
- honchoukanishoushinsugoroku
- 絵師・著者名
- 一猛斎 芳虎(歌川 芳虎)/画・万亭 應賀/著
- Creator
- 落款等備考
- 一猛斎 芳虎画・万亭 應賀著
- 板元・製作者
- 上州屋 重蔵
- 制作年和暦
- 弘化4年から嘉永5年
- 制作年西暦
- 1847-52
- 書誌解題
- 資料名1
- 本朝官位昇進双六
- 資料名2
- 史料名1よみ
- ほんちょうかんいしょうしんすごろく
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- honchoukanishoushinsugoroku
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 本朝官位昇進双六
- 絵師・著者名
- 一猛斎 芳虎(歌川 芳虎)/画・万亭 應賀/著
- 絵師・著作者名よみ
- よしとら (いちもうさい よしとら/うたがわ よしとら・まんてい おうが)
- Creator
- 管理No.
- 00001231
- 管理No.枝番号
- 000
- 落款等備考
- 一猛斎 芳虎画・万亭 應賀著
- 板元・製作者
- 上州屋 重蔵
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 弘化4年から嘉永5年
- 制作年西暦
- 1847-52
- 制作年月
- 弘化4年から嘉永5年正月
- 書誌解題
- 判型・形態
- *
- 印章の有無
- 名主2
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- おもちゃ絵
- 内容2
- ゲーム
- 内容3
- 双六 官位
- テーマ
- 官位とは国家の役人の官職と位階を示す。本来、この官職を覚えるために作られたとされ、中国にもあり、ここでは「本朝」と付けてある。むろん官職・位階の名称を覚えるだけではなく、正月遊びとして地位の昇進や将来の栄達、立身出世を願って遊ばれた。同類の「官職昇進双六」には寛政10年刊行のものもある。
各官位ごとに職務内容や地位をくわしく解説してあり、昇進を楽しみながら、官位に関する知識を得ることができる。
- 具体物
- 「ふりはじめ」は、衣冠束帯で朝廷に伺候する高宮。「上り」は「帝王」で、みかどとルビがつけてある。天子の姿は、御簾でかくしてあり、皇女又は皇后と女官のみ描かれている。あとの26の枡目には下から上へと、位階順に官職が紹介されている。下段右から「弾正」は洛中の巡検役、「主計頭」は算盤で戸口算数の計算、「主税頭」は年貢の上納「衛士」は禁中でたき火をたいての護衛である。上位になると、衣冠東帯の大礼服で座っているだけであるが、各官職ごとに業務内容を記してある。
袋:絵は亀が蓬莱山を背負って海に遊ぶめでたい図である。この亀は長生きして尾に海藻がつき、
蓑のようになった「みのがめ」で、長寿の象徴。背中の蓬莱山は、松竹梅が茂り、不老不死の仙
人が住むという理想郷。ともに中国の伝説に由来し、長寿を願うめでたい図像として、五月飾りな
どに使われた。背景の海上には、大きな太陽がうっすらと浮かび、日の出の状景である。
- Comments
- 位置づけ
- 朝廷の複雑な官職を知るとともに、職種にかかわらず、昇進出世を願った双六で、出世双六の基本タイプの一つ。道中双六と並んで、「上り」までのステップが明確に示された、代表的な双六。
- 讃・画中文字
- 左大臣 関白 上り 帝王 摂政 太政大臣
参議 中納言 大納言 准大臣 内大臣 右大臣
弁官 侍從 少将 中将 大将 少納言 将監 監物 内記 検非違使 蔵人 史
衛士 主税頭 ふりはじめ 主計頭 弾正
枡目内の官職説明文要解読
(右から1列目)
太政大臣(だいじょうだいじん):この官は天使の御師範にて 天使をたすけ万機をたすけおさむるをつかさどるなり 今は大相国と称すなり
右大臣(うだいじん):左大臣関白のときは そのしょく(職)にかはりて 左大臣のごとく あまたの政(まつりごと)をつかさどりたまふなり
少納言(せうなごん):このくらいは のこるをひろひ うけたるをおぎなう任なり 嵯峨帝 弘仁年中 只○(鈴?)印等のことを つかさどらしむ
史(し):中古より 小槻の宿称をもって一史とす 宮中のことをおこなふゆへに官務といふ 大政官の文書ことごとくこれをしるす
弾正(だんじやう):このやくは らくちう(洛中)をじゆんけん(巡検)して ひぎをただし あらためるを つかさどるなり
(右から2列目)
摂政(せつしやう):天子にかはりて 万機の政をつかさどり玉ふ いにしへ神功(じんごう)皇后 また聖徳太子 また藤原の忠仁つとめ玉ふ これを摂政のはじめといふ
内大臣(ないだいじん):このくらゐは 左右の大臣の上に列せしが ひさしく絶(たへ)ぬ 光仁帝の朝に藤原の良継 魚名等(うおなとう)をもって内大臣とす これより左右の大臣の下となれり
大将(たいしやう):大将は武官の極官(ごくかん)なり 平城天皇二年 藤原の内麻呂をもって左大将とし 坂の上の田村丸をもって右大将となしゐふ これを左右(さう)の大将のはじめなり
蔵人(くらんど):蔵人は地下(ぢげ)の諸太夫なり 正六位を極官とす
主計頭(かずへのかみ):このやくは戸口いんすうを算劫(さんかん)することを つかさどるなり
(右から3列目)
皇帝(みかど):天子の御名を天皇.皇帝主上当今至尊.陛下.御門.朝廷衛位聖朝.聖上.聖皇.御一人皇(ごいちにんすべらき)などともあがめ申す.出(いで)玉ふを御幸(みゆき)といひ 位をつぎ玉ふを御即位といひ 御ことばを倫言といひ おふせいださるを勅定といひ 御自筆をしんかんといひ おぼしめしを叡慮(ゑいりよ)といひ いかり玉ふをげきりんといひ 位をのがれ玉ふを仙洞(せんとう)と申し奉るなり
准大臣(じゆんだいじん):准大臣は内大臣の下にて大納言の上にいましゐふ御身なり
中将(ちうじやう):中将は左近衛右近衛中将といつて 兵具をたいし 大将の下に列してしたし 天子をまもるやくなり
検非違使(けびいし):けびいしは断獄(だんきよく)刑法(けいぼう)公事(くじ)訴訟(そしょう)をつかさどるやくなり
(右から4列目)
大納言(だいなごん):大臣とまじはりて 天下の政をおこない もし大臣ふさんのときは 大臣にかはりて その事をおこなふゆへ 亜相(あさう)と称して もつとも重職(ぢうしよく)なり
少将(せうしやう):少将は左右の少将というて五位の殿 上人譜弟(しやうにんふてい)の公達(きんだち)この官に任ずといふ
内記(ない):大内記(だいないき)小内記(せうないき)これを内史局(ないしきよく)といふ 詔勅(じやうちよく)宣下の出記(しよき)するやくなり
(右から5列目)
関白(くわんばく):天子のみことのりを奉りて 天下のまつりごとをとりおこなひ 人臣(じんしん)の上にい○すがゆへ 御一人とも申すなり 御父を太閤と申し 御祝髪(かざりをとり)玉ふを弾閣(ぜんかく)と称し奉るなり
中納言(ちうなごん):大臣大納言のことばをついで下にのべ また上にまうしあげることを つかさどり ゐふなり
侍従(じじゆう):少納言に任ぜらるる人 この官を兼て 天子の近習(きんじゆ)して のこれるをひろい かけたるをおぎなひ ゐふなり
監物(けんもつ):けんもつは 禁中の諸御門の鍵を つかさどるやくなり
主税頭(ちからのかみ):年貢を上納することを つかさどるやくなり
(右から6列目)
左大臣(さだいじん):あまたのまつりごとを奉行し玉ふゆへ 一の上と申すなり 御不参(ごふさん)のときは つぎの大臣これにかはりて つとめ玉ふ 竹内宿称(たけのうちすくね)より大臣の号はじまれり
参議(さんぎ):参議は四位以上の才ある人をゑらび 勅を奉り 宮中のまつりごとを参議(まじはりはかる)といふところなり
辨官(べんくわん):宮中のことをとりおこなふ重職なるゆへ 文才のひいでたるものをゑらびいださることなり
将監(しやうげん):将監は兵具をたいして禁中を守護するやくなり
衛士(ゑじ):禁中のおにわにて篝火(かがりび)をたくものなり
- 自由記入欄
- 遊び方「飛び双六」
・同類の「官職昇進双六」(寛政10年、123.5×105.2センチ)は、201もの枡目で構成されており、人物ないしはその役職にふさわしい品物で官職を示している。采も数でなく「祚、品、位、階、等、級」の六つの目になっている。(「絵すごろく」山本正勝より)
- 史料分類
- 絵画
