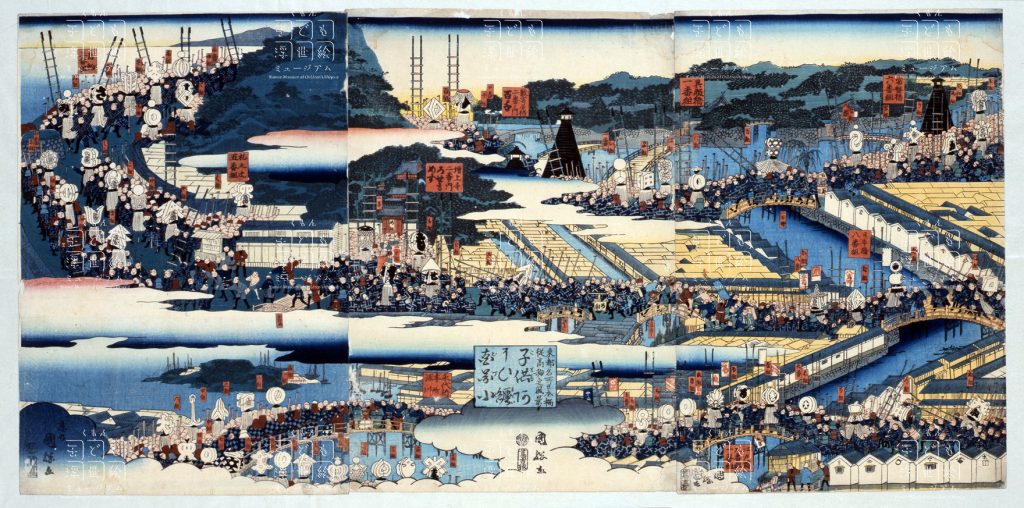
子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小
文久3年 (1863)
- 資料名1
- 子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小
- 史料名1よみ
- こどもあそびまといごっこ
- 史料名Roma1
- kodomoasobimatoigokko
- 絵師・著者名
- 國綱(歌川 国綱)
- Creator
- 落款等備考
- 國綱画
- 板元・製作者
- 蔦屋 吉蔵
- 制作年和暦
- 文久3年
- 制作年西暦
- 1863
- 書誌解題
- 資料名1
- 子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小
- 資料名2
- 史料名1よみ
- こどもあそびまといごっこ
- 史料名2よみ
- 史料名Roma1
- kodomoasobimatoigokko
- 史料名Roma2
- Title
- Alternative title
- シリーズ名・代表明細
- 子どもあそび 纏ごっこ
- 絵師・著者名
- 國綱(歌川 国綱)
- 絵師・著作者名よみ
- くにつな (うたがわ くにつな)
- Creator
- 管理No.
- 00001306
- 管理No.枝番号
- 000
- 落款等備考
- 國綱画
- 板元・製作者
- 蔦屋 吉蔵
- 彫摺師
- 制作年和暦
- 文久3年
- 制作年西暦
- 1863
- 制作年月
- 書誌解題
- 判型・形態
- 大判3枚続
- 印章の有無
- 年月改 版元
- 印章内容
- 複製フラグ
- 種別1
- 木版浮世絵
- 種別2
- 錦絵
- 種別3
- 内容1
- 子ども絵
- 内容2
- 遊戯絵 やつし 名所絵
- 内容3
- 火消し 行列 行進 名所@
- テーマ
- 火消には定火消、大名火消、町火消の三種があった。これは町火消の配置を江戸の鳥瞰図に示したものだが、人物を子どもにしてあるのは、火消を浮世絵で描くことは禁止されていたから。町火消は「いろは四十七組」からなるが、一番から十番までの大組に編成されていた。
- 具体物
- 右図の中央には日本橋川が流れ、下から江戸橋、日本橋、一石橋が並び、江戸城外堀へと続いている。左奥の呉服橋が一番組となっている。中図の下は永代橋で、題字の上に新ばしがあり、左上方には木々に囲まれ増上寺がある。右手には黒い物見櫓が建っている。左図下部は永代橋と隅田川河口の佃島。雲形の上には金杉橋があり、ここから上部の高縄の高台へと続く。全体に火消装束の人々が持つはしごやとび口、それに各組の纏もきちんと描いてある。
- Comments
- 位置づけ
- 火事場で活躍する火消しは子どもたちにも人気があり、子ども見立の火消がいくつも作られている。子どもたちは、纏によっていろは四十七組を覚えたのであろう。
- 讃・画中文字
- 子供あそひまとい纏ご御ず図こ小
*右上から左下に向かって翻字。
常盤橋 六番組
呉服橋 一番組
日本橋 八番組
江戸橋 九番組・十番組
数寄屋橋 二番ノ門 百・千(百組・千組)
増上寺 二番ノ門 ろ・せ・も・め・す(ろ組 す組)
(中央タイトル)
東都名所日本橋、
従高輪之風景(高輪よりの風景)
子供あそひ纏御図小
永代橋 本所 深川
高輪三 番組
札之辻 五番組
- 自由記入欄
- 史料分類
- 絵画
