
暑い日が続く時こそ、すずしく見えるよそおいを心がけたいもの。実は江戸時代の人々も、大変なおしゃれ好きでした。例えば季節に合った素材や色、文様を知ることは基本の一つです。年齢などによっても、着物の仕立てや髪型、おけしょう法が変わります。
こういったおしゃれの情報や、はやりのよそおいをいち早く伝えるのも、浮世絵の大切な役割でした。カラフルで、価格も今の雑誌1冊程度、まさに江戸っ子向けのファッション誌だったのです。
ここにも、最新流行の衣装を着た、若い女性が描かれています。白、水色、茶色の3色で段々になったデザインがすずしげです。おめでたい「宝づくし」などの文様や、えりもとの「絞り染め」がすてきですね。
お皿には、砂糖で作った金魚が乗っています。「金花糖」と呼ばれるきれいなおかしで、それをのぞきこむ子どもも、当時の幼児らしいユニークな髪型をしています。
もう一つの見どころは背景です。当時流行の最新のしま模様(ストライプ)を提案しているのです。「この生地で着物を作ったらすてきよね!」「きっと似合うよ!」など、浮世絵を見ながらはしゃぐ声が聞こえてきそうですね。

誂織当世島 〈金花糖〉(三代歌川豊国)弘化1-3年(1844-46)
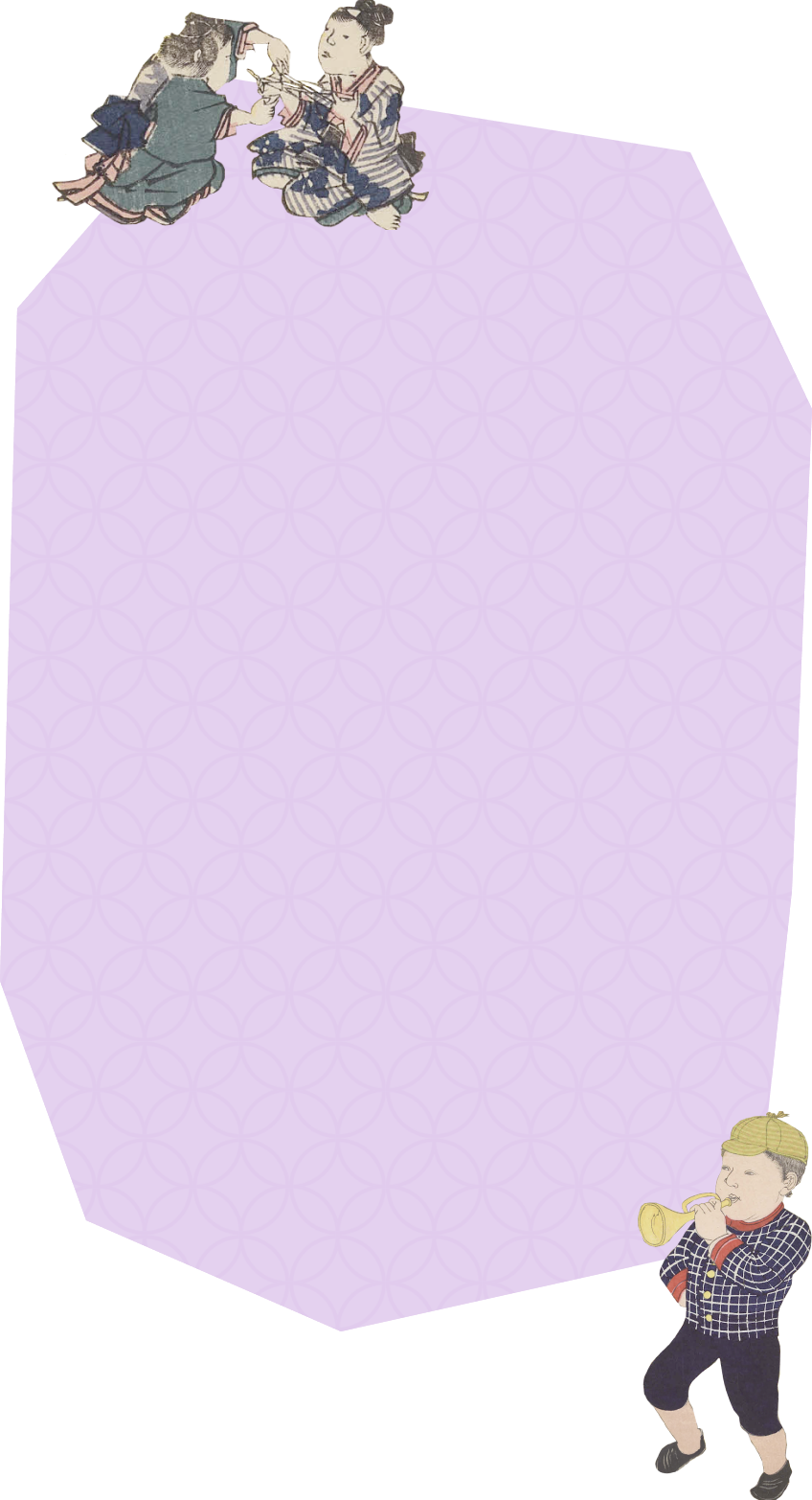
大人向け解説
しま模様を粋に楽しむ
ストライプ、ボーダー、チェックなどさまざまな呼び名がある模様も、江戸時代には縦じま、横じま、格子じまと、全て「しま」柄とされていました。
当時は幕府から、ぜいたくをいさめる「奢侈禁止令」がたびたび出されました。このような中で、色の組み合わせや模様の幅で印象が変わるしま柄は、江戸の庶民に大人気でした。
本図は「誂織」とあるように、オーダーメードの織物の見本帳の役割も果たしました。「当世」は今風、「島」は遠い異国の島から来た渡り物の意で、しま模様を指します。粋でおしゃれなしま柄に、江戸っ子たちは遠い異国への憧れも込めていたのですね。
