
大きな剣をふり上げた、真っ赤な鍾馗さま。きりりとした表情で、とても強そうですね。にらみつけるその相手は、いったいだれでしょう?
褐色のはだにトラの毛皮。爪は長くのび、頭にはとがった角が。どうやら、小さな鬼のよう。ちょっと弱そうですが、実は病気をもたらす怖い鬼なのです!
江戸時代にはさまざまなはやり病がありましたが、高熱が出る天然痘は、子どもの命をうばうおそろしい病気でした。疱瘡と呼ばれたこの病から子どもを守るため、大人はさまざまなくふうをしました。
この絵も、親が子どもに買いあたえた、「疱瘡絵」と呼ばれるお守り代わりの版画です。中国のお話で、皇帝の病魔を退治したという鍾馗さまを、疫病がきらう赤色で刷っています。まくら元に貼った後は、神社に納めたり、川に流したりしたため、ごくわずかしか残っていません。
わが子が病にかからぬように、または軽くすむようにと願いをこめた疱瘡絵。そこには、親の深い愛情が感じられます。今は医学の進歩で、みなさんを守る薬が開発されていますが、健康には毎日のくふうが大切。うがいや手洗いも忘れずに、元気に過ごしてくださいね。

七変化之内 朱鍾馗 関三十郎(歌川豊国)文化後期(1804-18頃)
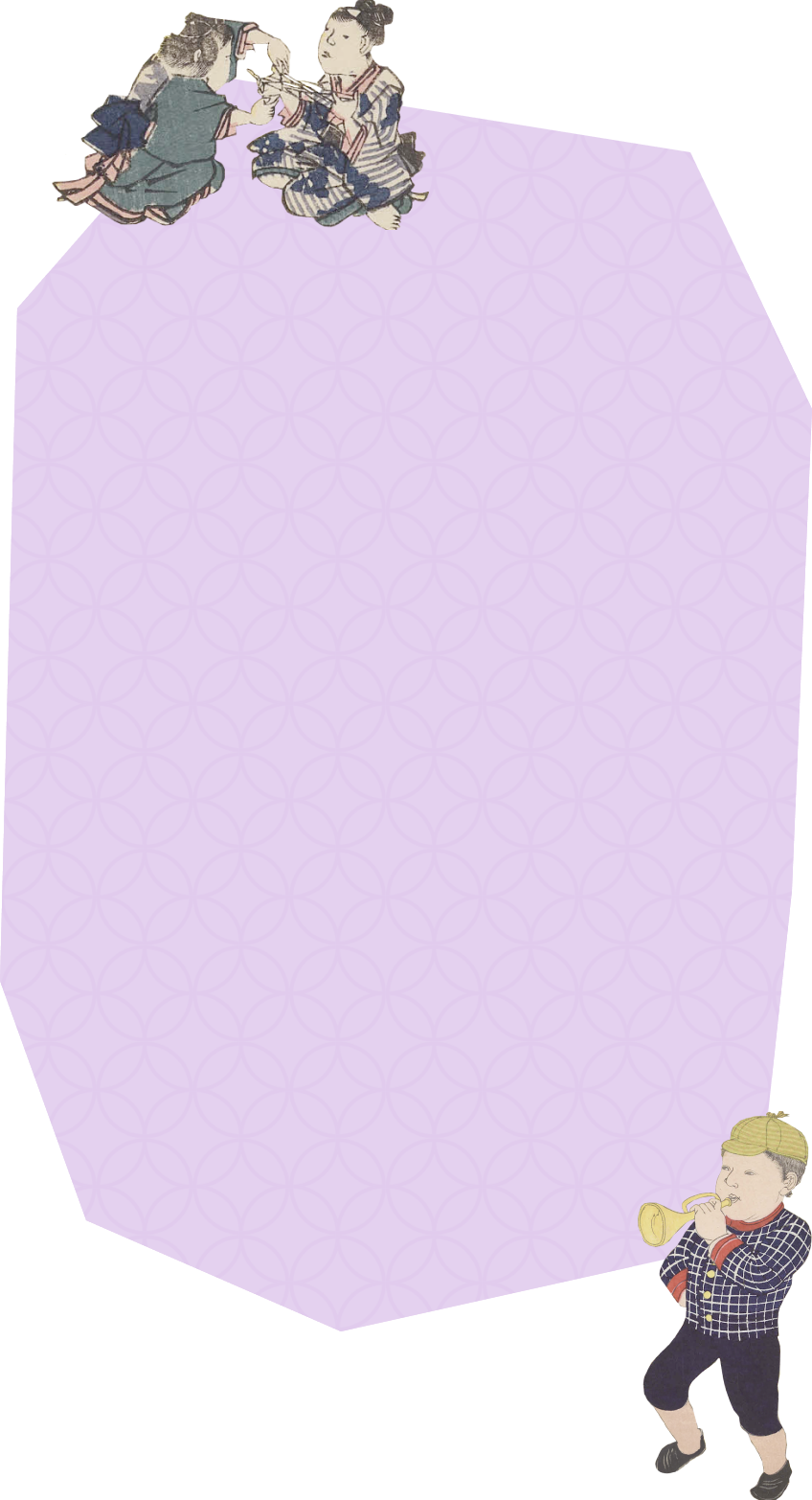
大人向け解説
人気役者が演じた鍾馗さま
浮世絵には美人画、役者絵など多様な主題があり、中には複数の要素を持った作品もあります。実は本図にも、「疱瘡絵」の機能に加え、「役者絵」の楽しみもあるのです。画中の文字から、この鍾馗さまは江戸の人気役者、二代目関三十郎(1786~1839)と知れます。1人で七つの役柄を踊り分ける「七変化」のうち、鍾馗を演じているのです。道理で立ち姿もりりしく、ポーズも決まっていますね。
紅の濃淡で刷る疱瘡絵が多い中で、墨、黄、緑などの色を重ねた点にも工夫がみられます。病よけの絵を買ってもらう子どもの好みか、はたまた親が役者のファンなのか。親子で楽しく選ぶ姿が見えるようです。
