
デザインやテーマが楽しい「浮世絵」は世界中で大人気! 中でも、江戸時代にとても人気だった喜多川歌麿には、今も多くのファンがいます。
きょうの主人公は、こしにおもちゃの刀を差した、元気な男の子。武士のイメージなのでしょう、家紋入りの幟をかざり、5月5日の端午の節句と分かります。
となりはお母さん。お祝いに来たお客さまに、あいさつをしています。よく見ると眉毛がなく歯を黒く染めています。これは当時の、子どもを産んだ女性のおけしょうです。
後ろはお姉さん。伸ばしかけの前髪を赤い布で結んでおり、年は十代の前半でしょう。かかえているのは、おめでたい熨斗もようの布をかけた重箱。絵の上部には、菖蒲や粽といった、端午の節句にゆかりの物の説明があります。重箱にも、お客さま用のおいしい粽が入っているのでしょう。
幟に描かれた男性は「鍾馗」さま。病気や魔物を追いはらってくれるたのもしい神様です。天然痘などの病から子どもを守るとされた朱色で描かれています。子どもの成長や健康を願う家族の思いは、今も昔も変わらないのですね。

端午の節供(喜多川歌麿)享和頃(1801-04頃)
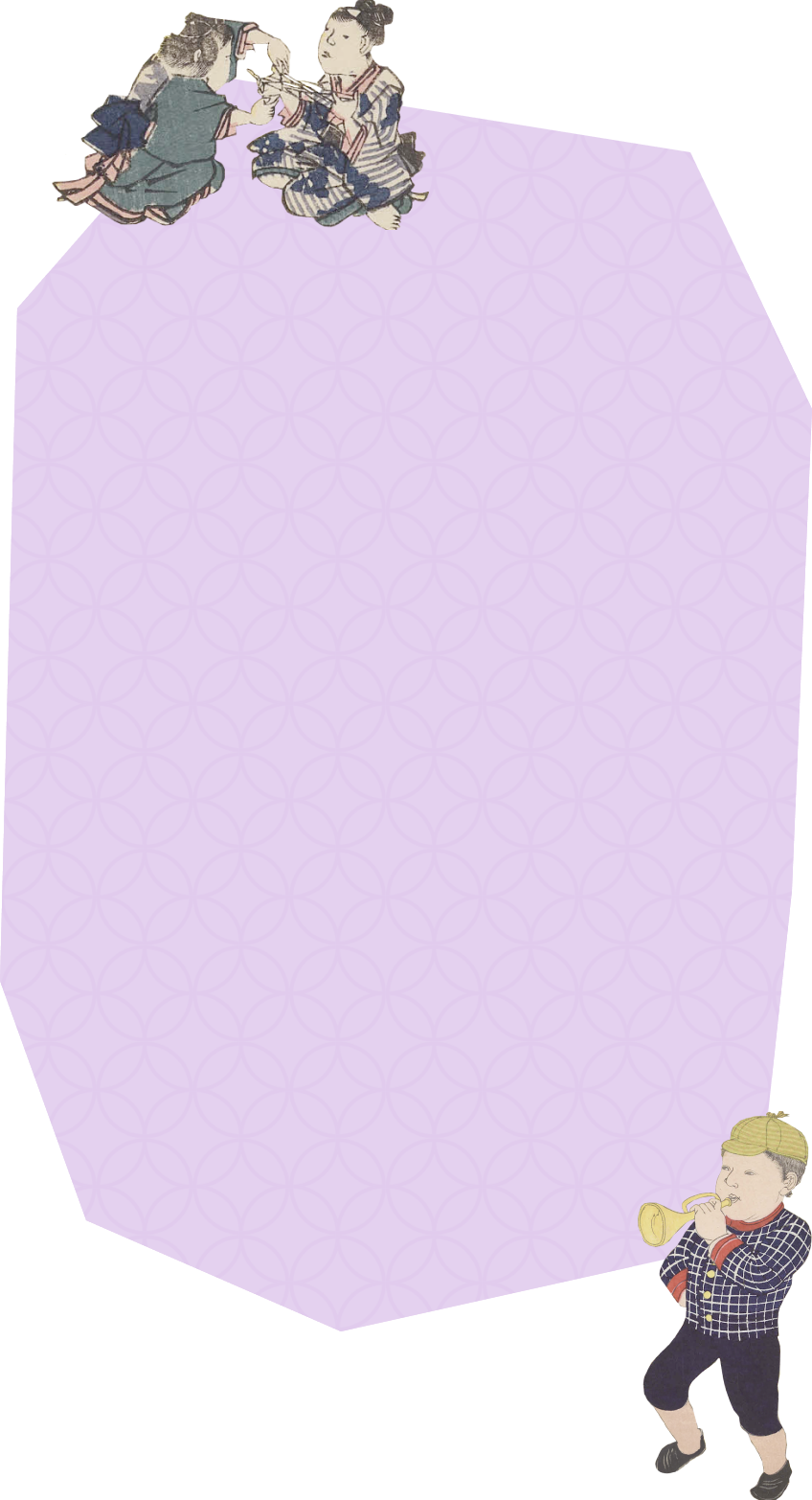
大人向け解説
装いは情報源?
「江戸のメディア」とも称されるほど、豊かな情報量を誇る浮世絵。装いを通じて人物の性別や年齢を理解することも、作品を楽しむ秘訣です。
江戸時代には生後7日で髪をそり、3歳前後で伸ばし始めたため、この男の子が幼児だと分かります。衣装にも見どころがあり、お姉さんの肩には、成長を見越して衣を調節する「肩上げ」の縫い目が見えます。男の子の着物の柄は、当時1番人気の歌舞伎役者、市川團十郎の家紋の三升模様。おしゃれですね。
時にファッション誌の役割も果たすほど浮世絵の用途は幅広く、着衣や髪形、化粧などが丁寧に描かれています。いつの時代も江戸文化の豊かさを伝える貴重なツールとなっています。
