
「怖いもの見たさ」と言うように、怖いけれど知りたいと思うことはありませんか? 江戸時代にあった怪談「ブーム」も同じです。
夜おそく、うす暗い部屋にいる子どもたち。明かりはあんどんのみ。火ばちを囲み、しんけんな顔で話に聞き入っています。中央の男の子が大きなジェスチャーで語り、物語は絶好調! どんな内容なのでしょう?
ヒントは、手首から先をだらりと垂らしたポーズ。そう、幽霊です。江戸時代に大流行した、「百物語」という怪談イベントの様子です。「暗い井戸からおそろしい声が…」などのこわ~い話に、「もう聞きたくない!」なんて言いながら、みんな先が気になって仕方がない様子。
「きゃあ!」、今度は後ろから大きなさけび声が。いたずらっ子が、ほうきに手ぬぐいや着物を着せて、ついたての後ろから差し出したようです。「本物のお化けだぞう!」。おどろいた少女たちは、そろってこしをぬかしてしまいました。
きもだめしにもなり、精神力を高めるとも言われた怪談のつどい。今よりもさらに「お化け」が身近にいた時代のもよおしです。今もさまざまな妖怪キャラクターが人気ですが、そのルーツとなる江戸時代の妖怪や幽霊を調べると、「怖くてかわいい」お化けの世界に、もっとはまってしまうかも?

新板子供遊びの内 百物がたりのまなび(歌川芳虎)天保後期(1830-44頃)
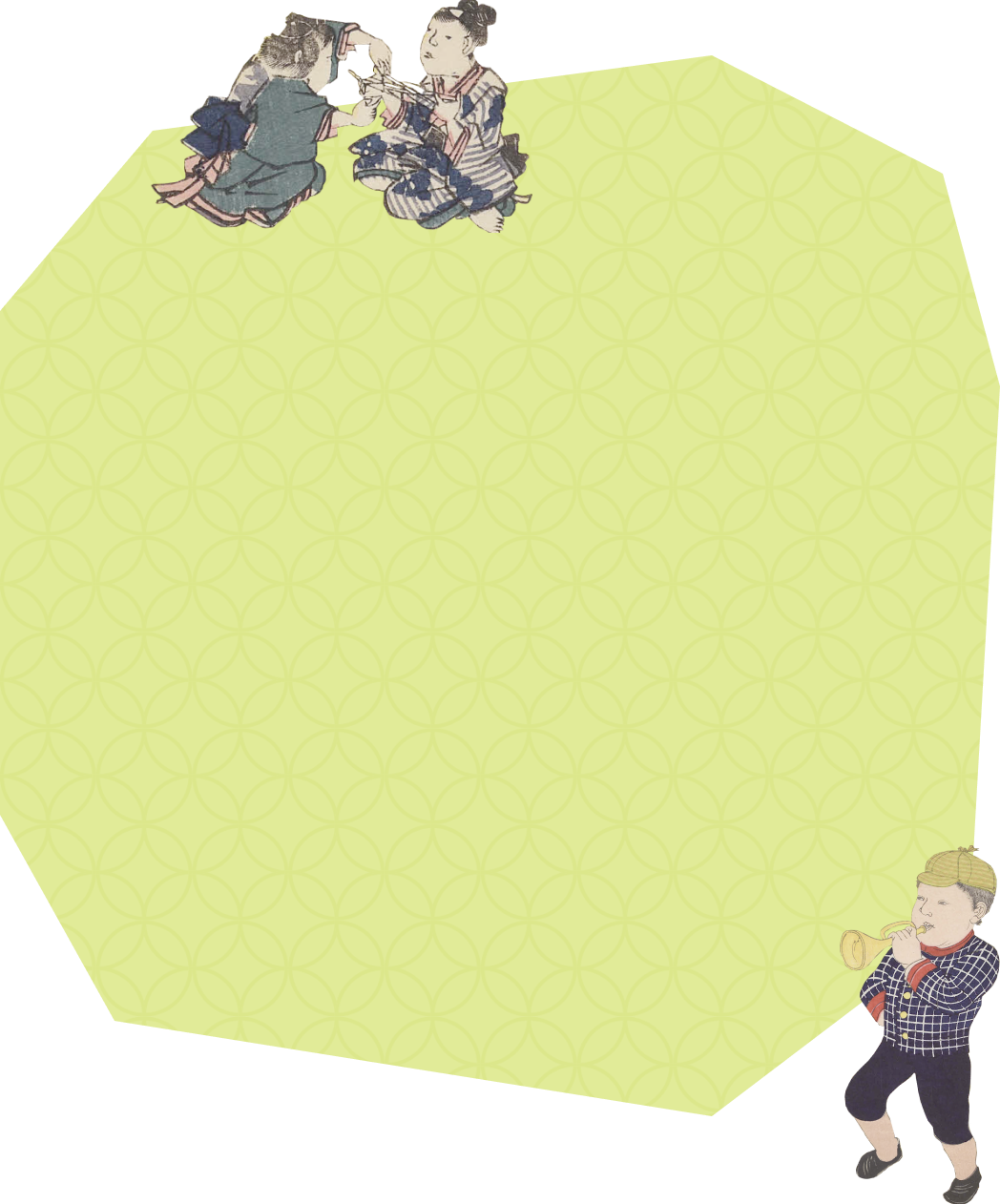
大人向け解説
「怖い」は楽しい
そのルーツは室町時代にもさかのぼるとされる「百物語」。日本の伝統的な怪談会で、寝ずの番をした夜伽たちが、合間に語った「巡り物語」が起源とも言われます。江戸時代には武士の心身の鍛錬になるともされ、庶民にも人気の催しとなりました。
深夜に数人で集まり、順番に怪談を披露するのが基本ですが、百話を終えると怪異現象が起こるとされました。演出で、行燈に青い紙を貼ることもありました。妖怪画の大家、鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』(安永10=1781=年にも、百話目に現れるという、長い髪と角を持つ鬼女「青行燈」の図が所載されています。
葛飾北斎らの人気浮世絵師も手がけた「百物語」。豊かな想像力で構成された怖くて楽しい世界を、楽しんでみてはいかがでしょう。
