
丸いお顔に大きな目、にっこりと笑うかわいい子ども。見ているだけで幸せになりますね。手足もふくよかで、健康そうです。実はこの男の子、古くから知られる「おめでたいもの」になりきっています。一体どんな役なのでしょう?
ヒントは、小道具や衣服、そして見る人を幸せにするこのえがおです。右手に釣りざおと真っ赤なタイ、頭に乗せた折れ曲がった烏帽子に注目! これらは福の神「えびす様」のトレードマーク。そう、この子は小さな神様なのです。子どもは宝と言われますが、ますますおめでたいですね。腹がけにも、亀のこうらやキクなどのえんぎの良いものが描かれています。
この浮世絵が描かれた江戸時代の後期には、7人の福の神をまつる「七福神信仰」が大流行しました。その1人、えびす様は海や漁業、商売の神様です。昔のこよみ、旧暦の10月20日(現在の11月中ごろから12月初めごろ)などに商売繁盛を祝うお祭りも行われます。
幸せを運ぶえびす様の特徴は、もう一つあります。それは、えがお。この子のようにニコニコした表情を「えびす顔」と言います。えがおは見る人の心も幸福にします。楽しいことを探して、すてきな「えびす顔」になってくださいね。

子供遊七福神 恵比寿(菊川英山)文化8年頃(1811頃)
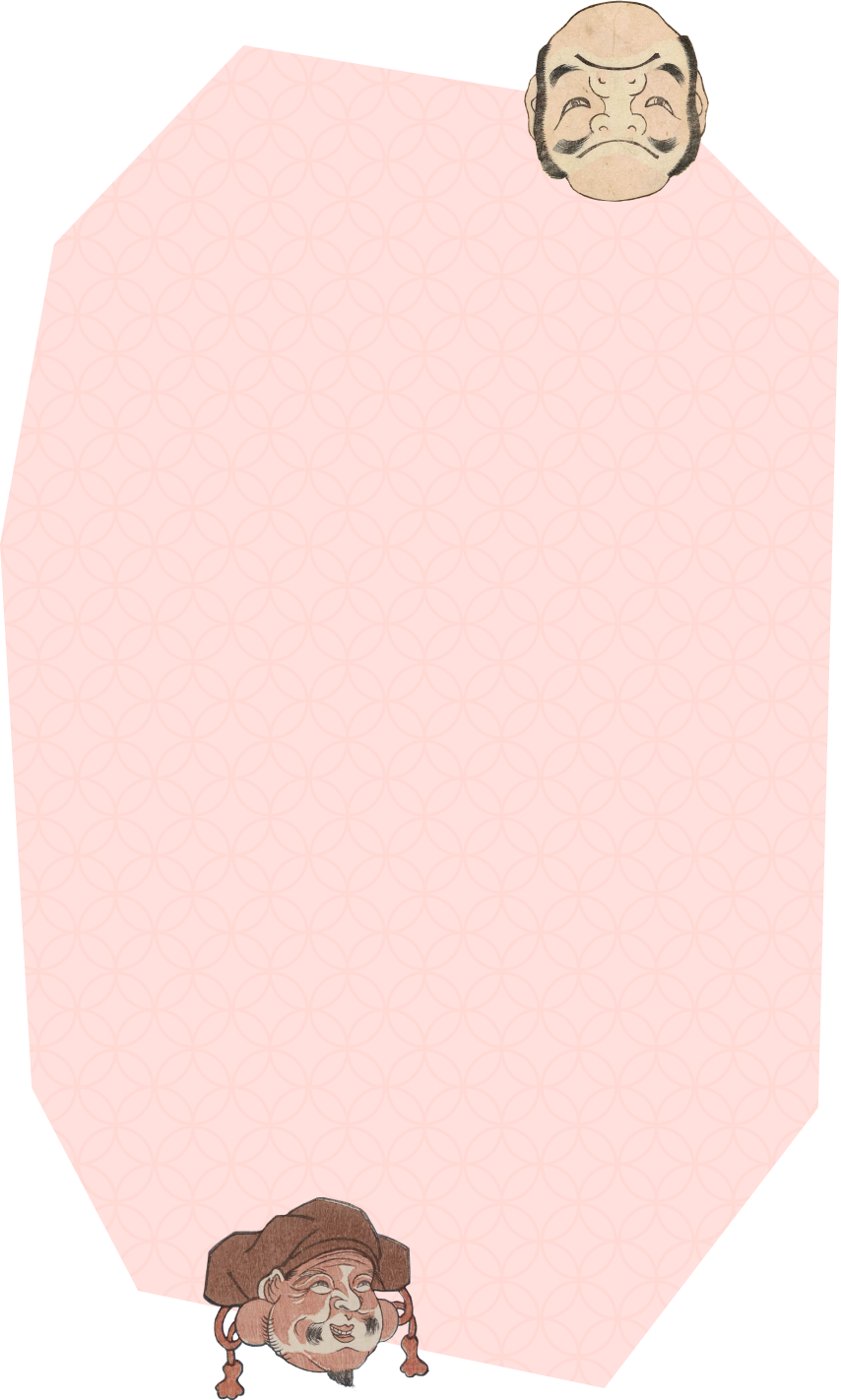
大人向け解説
七福神のヒミツ
「良いものは何でも取り入れたい!」と願う気持ちは、いつの時代も同じのようです。「七福神」信仰は、古くは室町時代にさかのぼるとされ、江戸時代には年始の「七福神めぐり」が流行します。良い初夢を見ようと、正月2日の夜に七福神が乗る宝船の絵を枕の下に敷いて眠る風習も浸透しました。
七福神と言えば、恵比寿の他に大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋の六神を加えた構成がよく知られています。このうち女性の神様は、音楽などの技芸に通じた弁財天のみ。
一方、共に中国の道教に由来する長寿神、福禄寿と寿老人を同じ神とみなすこともあります。寿老人の代わりに、容姿端麗、福徳安楽をもたらす女神「吉祥天」を加えるなど、時代や目的に沿って組み合わせも緩やかに変化しているのです。
