
たくさんの子どもに囲まれて、幸せそうなお母さん。まだ小さい赤ちゃんをだいて、にっこりとほほえんでいます。
色とりどりのおもちゃも見えます。子どもの健康を願う犬張子、音の出るたいこやうちわ、ままごとの道具もありますね。暖かい部屋の中で、きょうはどんな遊びを楽しんでいるのか、いっしょにのぞいてみましょう!
手前には、ねころがって本を読む男の子。少女が本をのぞきこんでいるので、絵本を音読してあげているのでしょうか。妹思いの優しいお兄さんですね。少女の着物の「ふくら雀」というかわいらしい雀の模様にも注目です!
中央には、あやとりをする2人。次の形をどうやって作ろうか苦戦する妹を姉がおうえんしています。やんちゃな妹には、ポップないちょう模様の着物が似合っています。姉の貝がら模様は、すてきな相手とめぐり会うラッキーアイテム。そろそろ恋するお年ごろでしょうか。後ろには、お兄さんにおぶわれてあまえる幼児もおり、みな仲良しです。
子どもの数は7人。日本には古くから7人の神様をまつる「七福神信仰」があります。大切に育てられてきた子どもたちを福の神に見立てているのでしょう。みなさんにたくさんの「福」がおとずれるよう、心からおいのりします。

東風俗 福つくし 子福者(楊洲周延)明治23年(1890)
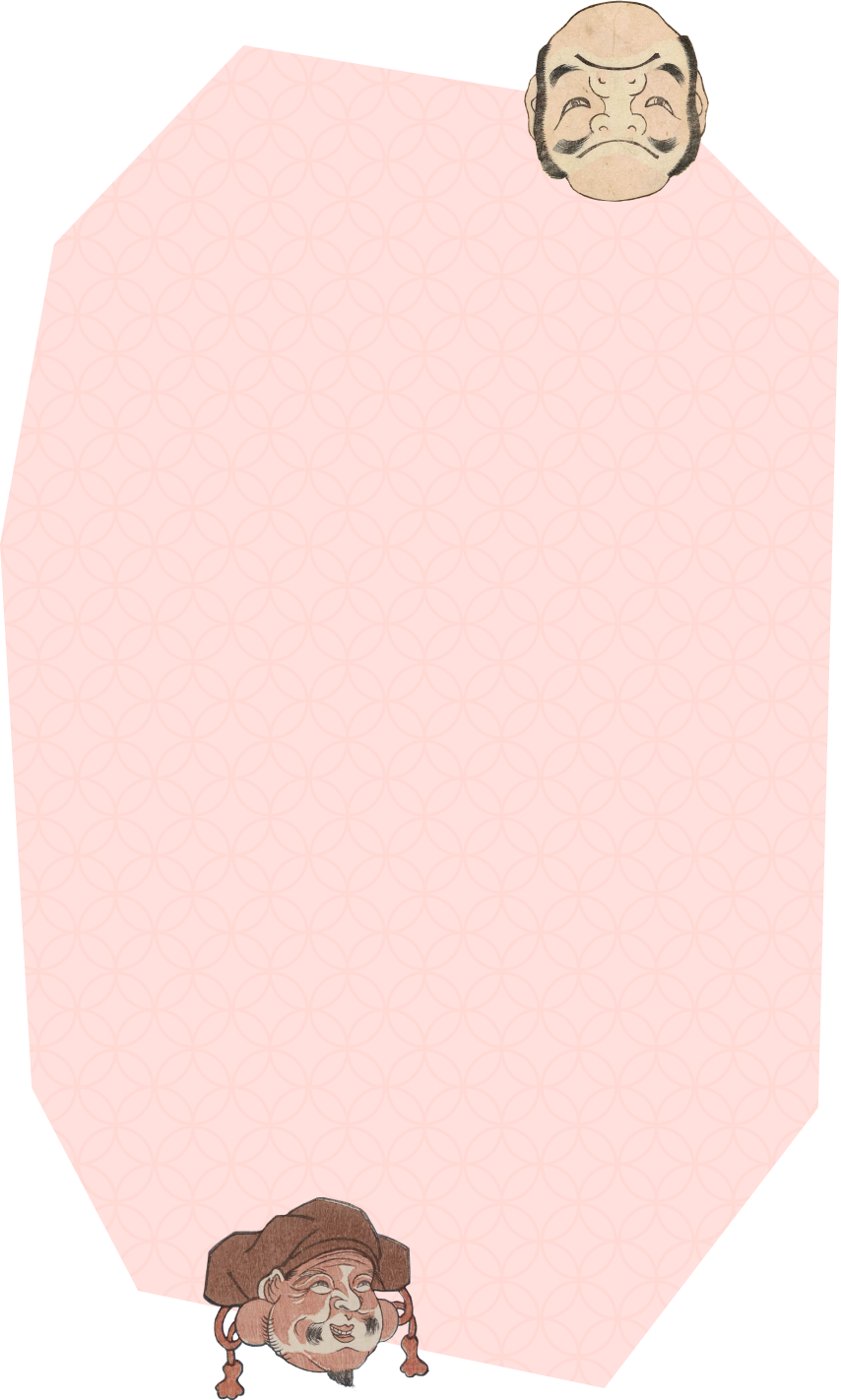
大人向け解説
新春も大忙しの「七福神」
おめでたいことを好む江戸の人々の間で、新春に七福神ゆかりの社寺を巡ることがブームになりました。正月二日の夜には、七福神が宝船に乗る図に、「ながきよのとおのねぶりのみなめざめ なみのりぶねのおとのよきかな」の回文(下から読んでも同じ文)を添えて枕に敷いて良い初夢を願う風習もあり、お正月にはとりわけ七福神の出番が多いようです。
七福神信仰は、一般に室町時代に始まるとされます。大黒天、恵比寿、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋の組み合わせがよく知られますが、寿老人と福禄寿を同一神とする説から、寿老人の代わりに容姿端麗な吉祥天を加える例もあるようです。
葛飾北斎や喜多川歌麿ら人気絵師も多く手がけた七福神、本図もその流れをくむ一例でしょう。
