
新春の景を描いたはなやかな浮世絵、青々とした若松と、清らかな水の流れが見えます。美しい女性たちが取り巻く中心に、男の子がいますね。まだ幼さが残る金太郎です。男子が月代をそり、大人の髪形に改める、元服という儀式の最中です。
元服は、古代の中国にならい、公家や武家で行われ、やがて庶民にも広まりました。金太郎は大きな「まさかり」で、落ちる髪を受け止めている様子。きんちょうしているようにも見え、おもしろいですね。
実はこの絵は、平安時代の武将、源頼光に見いだされた金太郎が従者となる場面のパロディーなのです。右上のおひめ様の衣装には、源頼光を暗示する「ささりんどう」の文様があります。女性の着物には四天王である碓井貞(定)光の「定」、2人の女性の打ちかけにも渡辺綱や卜部季武の「綱」と「末」の文字。強い武将を美しい女性に転じる点に、ユーモアが感じられます。
日本の「成年」は、明治9(1876)年以来20歳とされてきましたが、2022年4月に18歳に引き下げられました。江戸時代の男子の元服が15歳前後であったことを考えると、あながち、若過ぎるということはないのかもしれませんね。

金太郎元服の儀(歌川豊国)寛政期(1789-1801)
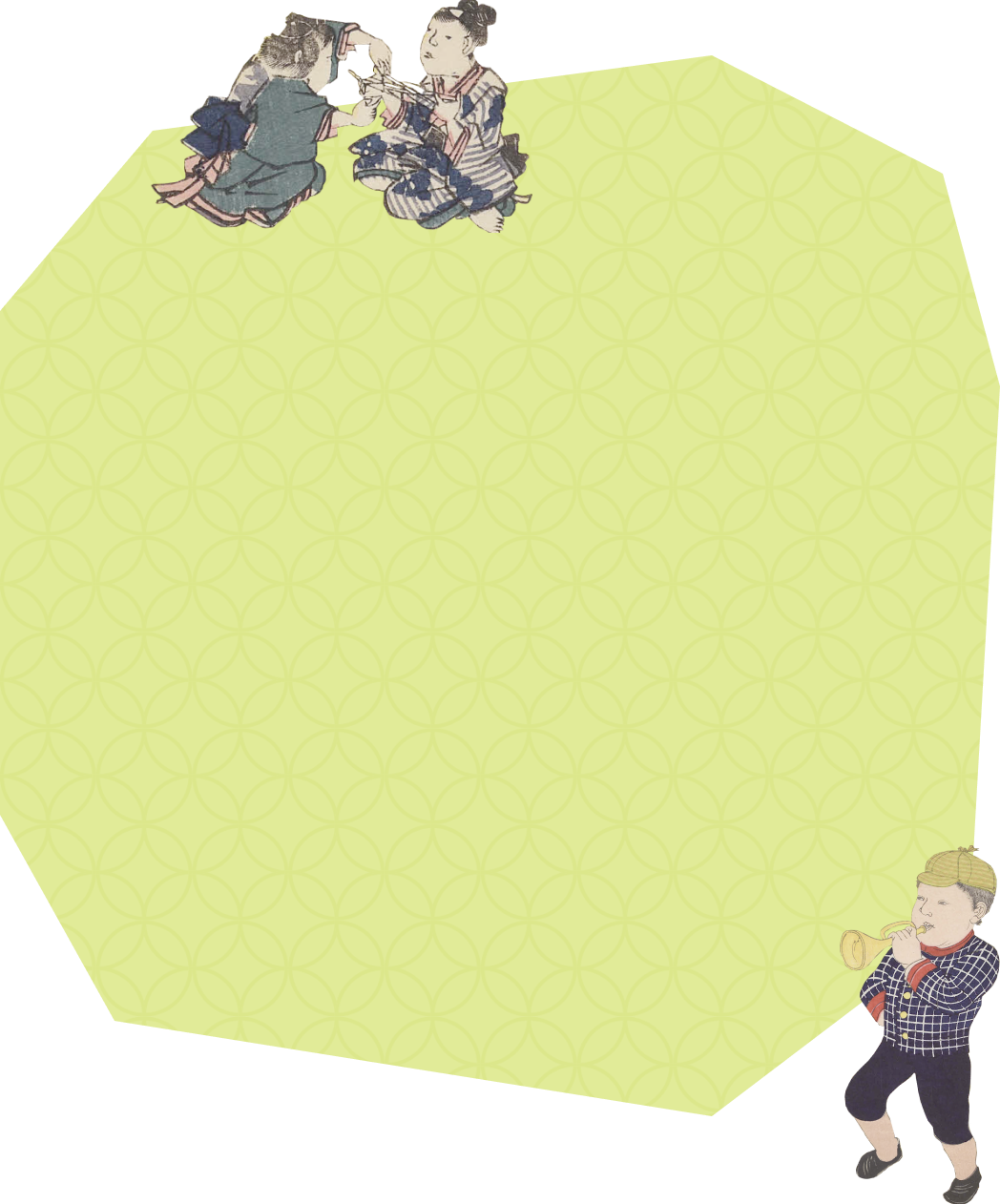
大人向け解説
歌川派隆盛の立役者
浮世絵の最大流派である歌川派、その隆盛のきっかけを作ったのが、本図の作者である初代豊国(1769~1825年)です。豊国は歌川派の開祖豊春に師事し、幅広いジャンルの作品を手掛けました。
活動前期にあたる寛政期(1789~1801年)は、浮世絵の黄金期と称されるほど活況を呈していました。役者絵では東洲斎写楽、美人画では喜多川歌麿らの絵師が活躍しました。豊国は流行を巧みに取り入れながら、幅広く愛される様式を構築したのです。
本図のすっきりとした立ち姿や、細かなポーズの描き分けにも、美人画や役者絵を得意とした豊国らしさが感じられます。豊国は国芳をはじめ多くの弟子を育てました。金太郎などを勇猛に描いた国芳の作品にも、豊国譲りの人体描写が生かされているのでしょう。
