
みなさんは、「初午」という言葉を聞いたことがありますか? 日本には古くから十二支にちなむ日付の呼び方があり、初午は2月の初めての「午の日」を指します。またこの日に、京都の伏見稲荷をはじめ、各地の稲荷神社で行われるにぎやかな祭礼も、こう呼ばれます。
今回の浮世絵も、このお祭りを描いています。ここは、江戸隅田川沿いにある三囲稲荷、真ん中に石の鳥居が見えます。この鳥居は低地にあり、対岸からはまるで土手にめりこんだように見えたと言います。人気のスポットで、初午の日には多くの人でにぎわいました。
鳥居を元気にくぐるのは、かわいい6人の男の子。今にも、にぎやかな声が聞こえてきそうですね。先頭の2人は、神様のお使いとされる白いキツネの人形を高くあげています。
右の2人は、大きな幟を持っていますが、鳥居をくぐれるのでしょうか? 後ろの子どもがせんすを手に、みちびいています。有名な歌舞伎役者が好んだ「三枡紋」のおうぎも、なかなかにおしゃれです。これから町をねり歩くのでしょう。
力を合わせて歩む子どもたちは、まさに今日の主役です。楽しい浮世絵の世界は、私たちにも元気をあたえてくれますね。

正一位三囲稲荷大明神(勝川春章)天明後期(1781-89頃)
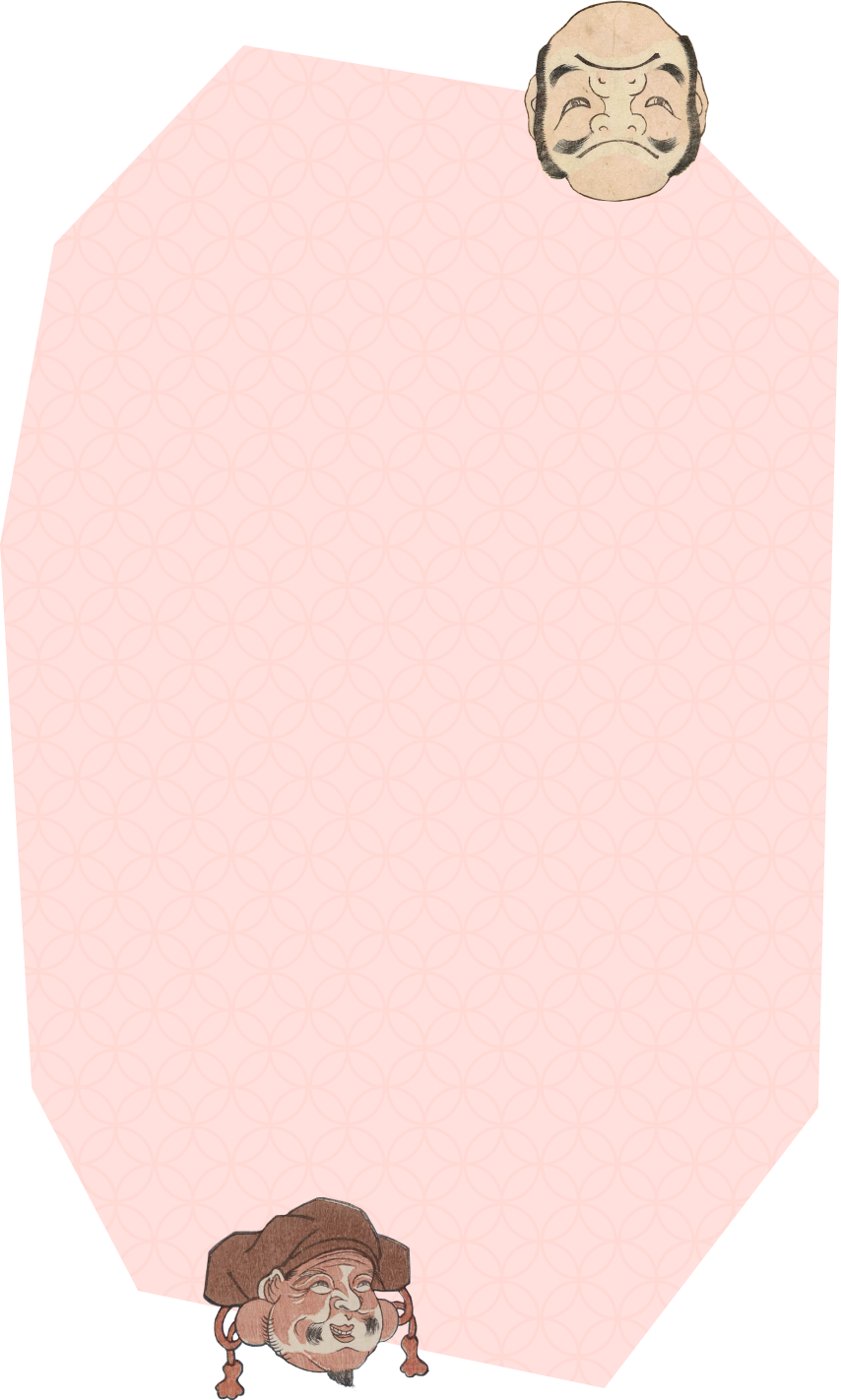
大人向け解説
暦の不思議
旧暦を用いていた江戸時代の「初午」は、2月の下旬から3月の中頃といった、少し春を感じる頃に巡ってきました。
この子どもたちの装いも、現代の感覚で見るといかにも寒そうですが、旧暦の情景であることを考えると、少々納得がいくかもしれません。それにしても、裾をはだけて手足を出して、元気な様子ですね。
絵師の勝川春章は、かの葛飾北斎の師で、役者絵や美人画といった人物画を得意としましたが、かわいい子どもを描いても天下一品です。加えて、景観表現にも長けていました。本図も自然な遠近法を用いた背景で、生き生きと遊ぶ子の姿が印象的です。隅々までじっくりと眺めると新たな発見があるのも、浮世絵の大きな魅力ですね。
